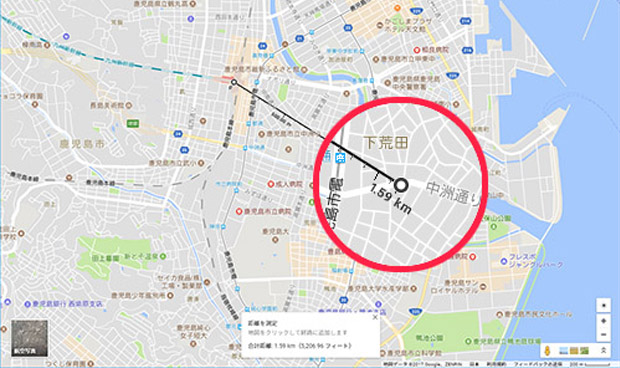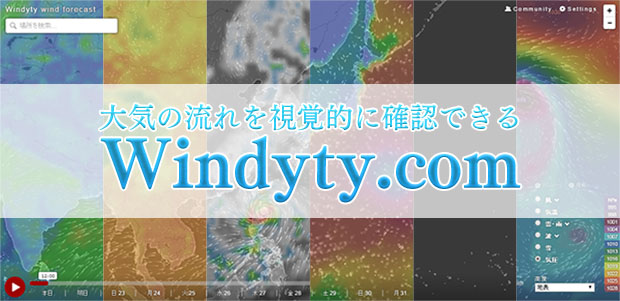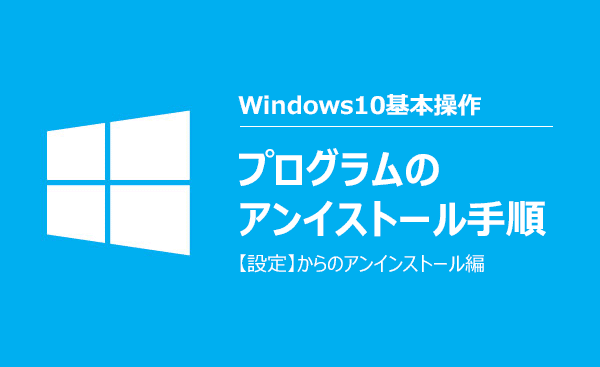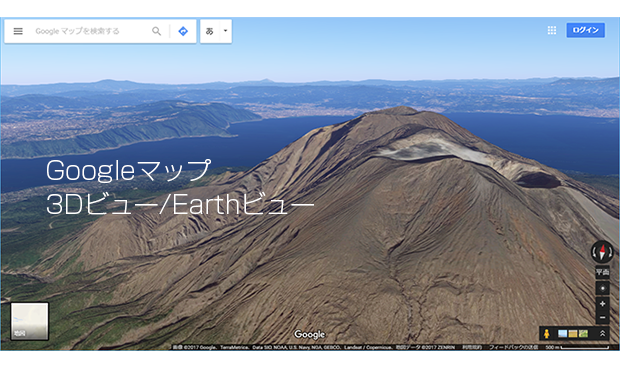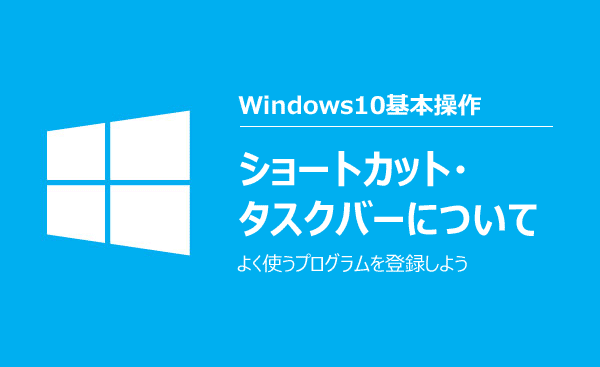最近、よく目にする言葉に「32ビット」「64ビット」というものがあります。
いったいこれは何を意味する数字なのでしょうか?
Windowsパソコンを購入するとき、32ビットと64ビットのどちらを購入すればいいのでしょうか?
ビット(bit)とは?
コンピュータが扱うデジタル信号が0と1で構成されていることはご存知の方も多いと思います。
この0や1など、一つ一つの最小単位のことを「1ビット」といいます。
身近なところでは、インターネットの速度を表す単位として、100Mbps(メガ・ビー・ピー・エス)、1Gbps(ギガ・ビー・ピー・エス)と書きますが、この「b」は、まさしくビットの略で、100Mbpsなら1秒間に100Mb(およそ1億ビット)の情報をやり取りできることになります。
32ビット と 64ビット の違い
単純に、32ビットと64ビットで「どちらがいいのか?」といわれれば、ほとんどの場合64ビットの方が優れた性能を発揮します。
この32・64という数字は232 、 264という、2のべき乗の数字であり、一度に扱えるデータの幅は、実際計算してみると大きな差があることがわかります。
- 232=4,294,967,296個
- 264=18,446,744,073,709,551,616個
32ビットと64ビットの違いによる主な性能差は、以下のとおりです。
| 32ビット | 64ビット | |
|---|---|---|
| 扱えるメモリの容量 | 最大4GB | 最大約171億GB |
| 扱えるハードディスクの容量 | 2TB | 約16,000,000 TB |
ようやく普及した64ビット
64ビット対応した最初のWindowsは、XPということで、かなり古くからありました。
しかし、64ビットが本格的に普及したのは、Windows7から、とかなり時間がかかっています。
その理由は、いくつかありますが、
- 一番重要なパソコンの心臓部CPUが、普及価格帯のモノも含めて64ビットに対応したこと
- 高画質なハイビジョン動画などの大容量ファイルを扱う機会が増え、64ビットのパワーで効率よく処理する必要性が増したこと
- 64ビットWindows上で、かつて動かなかった32ビットのソフトウェア(旧来の資産)をほぼ問題なくそのまま利用できるようになったこと
- プリンタなど周辺機器を動かすためのソフトウェア(ドライバ)が64ビットに対応したこと
などが挙げられます。
こういった環境が整ったことで、一気に64ビットが当たり前の時代になりました。
特段の事情がなければ64ビットを
先にも書いたとおり、旧来の32ビットMicrosoft Officeなども、ほぼ64ビットのWindows上で利用できるようです。
古い周辺機器では、64ビットのドライバソフトウェアが配布されていないものは、動かない可能性が高いです。
逆に32ビットのWindows上で、64ビットのソフトウェアは間違いなく動きません。
最近の市販のパソコンは、最初から4GBを超えるメモリを搭載していることも珍しくありません。
せっかくの性能を持て余さないためにも、特段の事情がない限り、今後パソコンを購入する時は64ビットを選択しておくことをお奨めします。